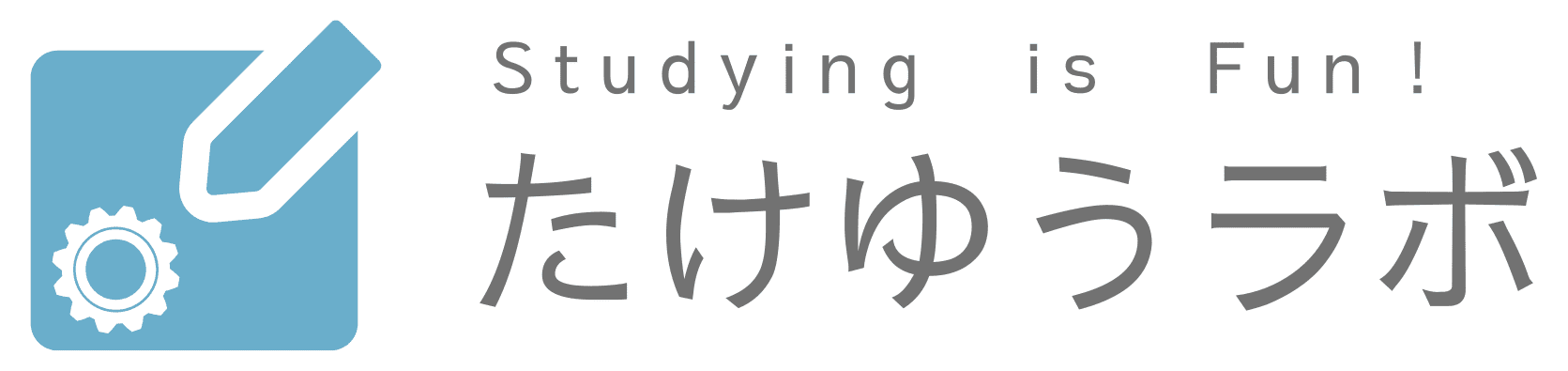スコープという言葉には「範囲」という意味があり、PMBOKガイドでは「範囲」の意味で使っています。
プロジェクトマネジメントでスコープとは、「仕様」まで含めた「作業範囲」や「責任範囲」を表します。
つまり、顧客要求を把握し、それに応じた適切な成果物を提供するという領域になります。
そんなスコープのマネジメントに関し、次の用語をざっくばらんに説明します。
実際の試験用語として厳密に参照されたい場合は、PMPOKや参考書をご確認ください。
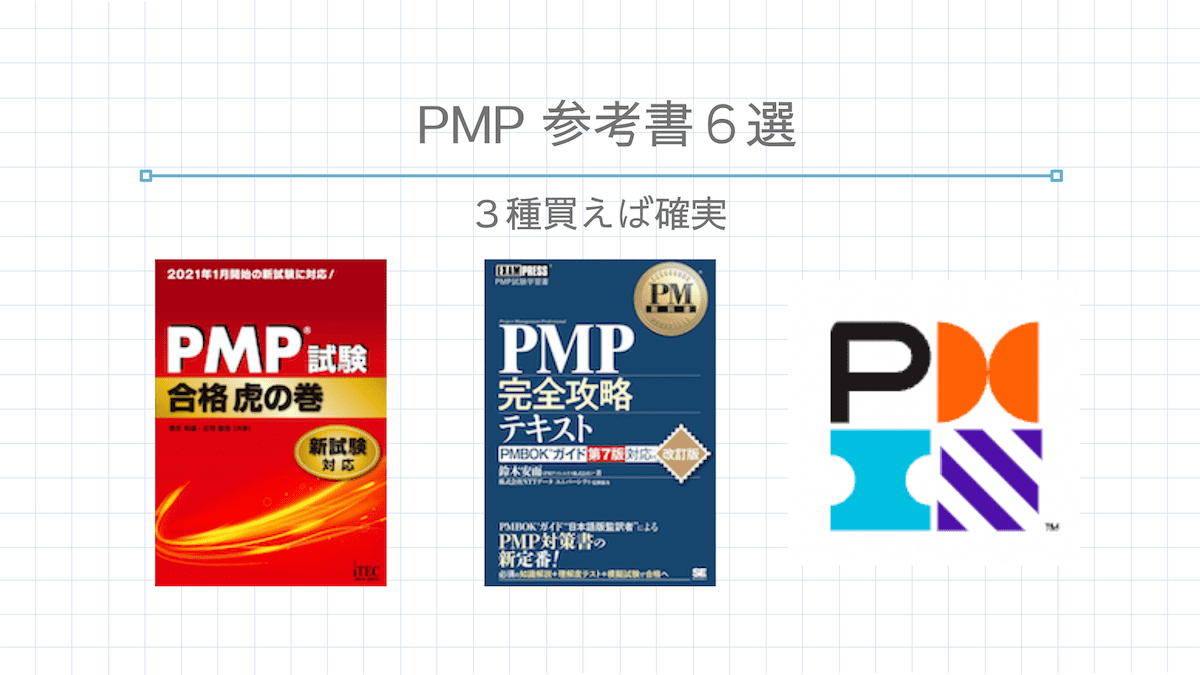
要求のマネジメント
要求のマネジメントとは?
要求のマネジメントとは、ざっくりと言うと
「お客さんの『こうしてほしい!』をちゃんと集めて、漏れなくブレずにプロジェクトに反映させる技術」
いわば、恋人とのデートプランを立てるようなもの。
「海に行きたい」「美味しいランチが食べたい」「日焼けはNG」
――これ、全部「要求(要件)」です。
要求のマネジメント5ステップ(PMBOK的な説明)
- 要求の計画(Plan Requirements Management)
どうやって要求を集めて、記録して、管理するかの決めルール。
👉「デートの前に、希望をLINEで聞いてとこ」みたいなノリです。 - 要求の収集(Collect Requirements)
客さん、ユーザー、ステークホルダーなどから要求を聞き出します。
👉まるで「彼女の友達にも調査して、理想のサプライズを探す」感じです。 - 要求の分析(Define Scope)を集めた
要求をもとに、どこまでプロジェクトでやるかを決定します。
👉「海に行って、水族館はOK。夜のバーベキューは今回は無理だな…」みたいに調整します。 - 要求の文書化(Create Requirements Documentation)
要求を正しく書面に残します。その後「言った・言わない」にならないように - 要求のトレーサビリティ・マトリクス(Requirements Traceability Matrix)作成
要求がどこでどう生きて来るか追跡できるように
要求管理でありがちなNG集(あるある)
- 「あ、それ言ってなかったっけ?」
→要求の収集ミス。
👉デート中「やっぱ夜景も見たかったな…」って言われて真顔になる。 - 「そんな要求なかったよね?」
→文書化不足。
👉「いやいや、絶対言ってたって!証拠はLINE!」みたいな論争に。 - 「この機能、誰の要求だけ?」
→トレーサビリティなし。
👉「なんで突然ビーチバレーの道具買ったんだっけ…?」状態。
PMP試験でのポイント
- ステークホルダーとの関係性を重視!要求はあくまでも期待を反映しているので、信頼関係が命。
- 変更管理とセットで理解しよう!要求は変わる。いやマジで変わる。恋人のような気持ち。
- ツールや技法もチェック
→インタビュー、ワークショップ、ブレスト、プロトタイピングなど
要求の管理は、「ステークホルダーが何を望んでいるか」を把握し、それをブレズにプロジェクトに反映させるための仕組みです。恋人とのデートですら、ちゃんと管理しないと「機嫌が悪くなってしまう(=プロジェクト失敗)」んです。予算何億のプロジェクトで、要求の管理をやらない手はない!
ユーザーストーリー
ユーザーストーリーとは?
ユーザーストーリーとは、ざっくりと言うと、
「ユーザーの立場から、“超シンプルに書いた短い物語”」
です。
これは、芥川龍之介でも村上春樹でもなく、
もっと軽くて実用的で、「つぶやきレベルの要件定義」のようなもの。
たとえ話:ラーメン屋アプリの場合
あなたは、ラーメン屋さんの注文アプリを作るプロジェクトのPM。
ここに出てきたユーザーストーリーがこれ:
「私は客として、並ばずに注文できるように。そうすればスムーズにラーメンを食べられるからだ。」
これだけ!
小説の一節、Twitterで言えちゃうレベルです。
ユーザーストーリーのテンプレ
私は(誰)として、(何を)したい。そうすれば(なぜ/何の価値)この3つが入っていればOK!
| 要素 | 意味 | 例(ラーメンアプリ) |
|---|---|---|
| 誰(Who) | どのユーザーですか? | 「私は客として」 |
| 何を(What) | したい? | 「並ばずに注文したい」 |
| どうして(Why) | なぜそれが大事ですか? | 「スムーズにラーメンを食べたい」 |
| 要素 | 意味 | 例(ラーメンアプリ) |
|---|---|---|
| 誰(Who) | どのユーザーですか? | 「私は客として」 |
| 何を(What) | したい? | 「並ばずに注文したい」 |
| どうして(Why) | なぜそれが大事ですか? | 「スムーズにラーメンを食べたい」 |
PMP試験として理解すべきことは
- アジャイルでの要求の表現方法
- 製品バックログアイテムのひとつ
- プロジェクトの範囲をスコープではなく価値で定義する考え方
先に「ユーザーが本当に欲しいもの」にフォーカスした手法です。
ユーザーストーリーは、ユーザー視点で価値に重点を置いた要求の表現方法。
堅実な「仕様書」ではなく、「ユーザーの声」をラフに形にするものです。
バックログの優先順位付け
PMP試験のアジャイル分野で出てくる「バックログの優先順位付け(Backlog Prioritization)」って、シンプルに聞こえるけど、いざ出題されると「え、どの順でやるのが正解!?」って悩ましいです。
まず「バックログ」ってなに?
まず「バックログ」とは簡単に言うと、
「やりたいこと全部書いている『やることリスト』」
でもただのリストじゃありません。
プロダクトオーナーの夢と妄想と現実が詰まった、無駄なToDoリストです。
バックログの優先順位とは?
バックログの優先順位とは・・
「この中で、どれからやる?何を一番大事にする?」を決めること。
ただし、決める際は「なんとなく」や「思いつき」は禁止です。
ハンバーガー屋でのバックログ考察
あなたがハンバーガー屋をオープンするプロジェクトのPMだとします。
バックログにはこんな項目が…
- チーズバーガーを追加する
- モバイル注文に対応する
- ハンバーガーの箱を金ピカにする
- フライドポテトにトリュフオイルをかける
- 期間限定でベーコン20枚バーガーを出す
これ、どれからやりますか?
見た目のインパクト?売上?コスト?お客さんの要望?
ここで優先順位付けのテクニックが登場します!
主な優先順位付けの考え方
1.ビジネス価値(ビジネスバリュー)
「それで売上や顧客満足がグンと上がる?」
👉 例:モバイル注文対応→ 消費性爆上がり!
2.リスクと機会(リスクの軽減 / 機会の実現)
「今やっとあと後々助かる?」
👉 例:モバイル注文の技術を今頑張って、他店舗展開が楽に!
3.依存関係(Dependency)
「これを先にやらないと、他のが進まない?」
👉 例:パティの規格変更がわら終わらず、20枚バーガー作れない…
4.コストと労力(労力 / コスト)
「めっちゃ時間かかる?すぐ終わる?」
👉金ピカの箱→コスパ最悪
優先順位の現場あるある
- 開発者:「やっぱ最初に金ピカの箱やっときましょ!」
→ 見た目は大事だけど…誰が買うんやそれ(笑) - ステークホルダー:「全部優先度“最高”で」
→ はい出ました。「全部大事」は「何も決まってない」と同義です! - プロダクトオーナー:「とりあえずカッコいいのから」
→ 感情も大事だけど、価値と根拠で語ろう!
優先順位付けは、「最も価値があるものを、最も早く届ける」ための技術。
アジャイルの価値観とズレたらNGです!
スコープベースライン
「スコープ・ベースライン(Scope Baseline)」も、PMP試験でバッチリ出るポイントです。
スコープ・ベースラインとは?
一言でいうと…
「プロジェクトで“何を作るか”の公式な決定版メニュー表!」
です。
あなたが「結婚式のウェディングケーキを作るプロジェクト」のPMだったとして、
- 「3段重ね」
- 「チョコレート味」
- 「フルーツ乗せ」
- 「名前入りプレート」
と決めたら、それがスコープ・ベースライン。
この内容は「そのうちブレないように」「勝手に変わらないように」 固定しておく、というわけです。
内容は3つのセットメニュー!
スコープ・ベースラインは3点セットで構成されます:
| 要素 | 概要 | 例(ウェディングケーキ) |
|---|---|---|
| スコープ記述書 | 何をやる/やらないかの詳細説明 | 「3段」「チョコ」「名前入り」など詳細に書いている |
| WBS(作業分解構成図) | どの作業で分かれるか、ツリー構造で分解 | 材料準備→スポンジ焼く→フルーツカット→デコる… |
| WBS辞書 | 各WBS要素の説明(仕様書的なやつ) | 「スポンジはココア味」「フルーツは季節のもの」など細かいところ |
| 要素 | 概要 | 例(ウェディングケーキ) |
|---|---|---|
| スコープ記述書 | 何をやる/やらないかの詳細説明 | 「3段」「チョコ」「名前入り」など詳細に書いている |
| WBS(作業分解構成図) | どの作業で分かれるか、ツリー構造で分解 | 材料準備→スポンジ焼く→フルーツカット→デコる… |
| WBS辞書 | 各WBS要素の説明(仕様書的なやつ) | 「スポンジはココア味」「フルーツは季節のもの」など細かいところ |
ケーキ屋で例えるスコープ・ベースライン
これを想像してみてください:
あなたがお客さんにケーキを届けるとして、口頭だけで「いい感じのケーキで!」って言われたらどうですか?
- あなた「3段で行きますね!」
- 客「いや、1段って言いましたけど?」
- あなた「チョコ味にしておきました!」
- 客「バニラって言ったじゃん!」
\修羅場/
このような事態を防ぐために「これが公式のケーキ仕様です!」とする文書が、スコープ・ベースラインなのです。
なぜ「ベースライン」なの?
「ベースライン」とは、比較や変更管理のための「ものさし」のこと。
例:
「スコープ・ベースは『3段ケーキ』だったけど、2段に変更するなら、ちゃんと変更管理プロセスずっとね!」
勝手に変更されたら、ケーキは倒れるし、予算はオーバーするし、嫁は泣きます。
あるある・やってはいけない例
- 「ちょっとだけトッピング増やしてもバレないでしょ」
→ 小さな「スコープクリープ」が命取り! - 「この変更、口頭で伝えたんで大丈夫っす!」
→ どこにも記録されてない!?PMP的にはアウト! - 「スコープ・ベースラインって、どっかにあった気がする…」
→ ベースラインが迷子になると、プロジェクトも迷子。
PMP試験として重要なポイント
- スコープ・ベースラインはプロジェクト・経営計画書一部
- 変更したいときは統合変更管理プロセスを必要あり
- スコープ管理において、「何をやる・やらない」を線引きするための核
- WBSとのが、**「範囲の定義→分解→管理」**という流れをしっかりと保持して強い!
- 「やること・やらないこと」を明文化!
- WBSとセットで、構造的に管理!
- 勝手な変更はNG!変更管理プロセスを通そう!
- ケーキだって仕様通りに作らないとブーケが飛んできます!
WBS
PMP試験ではおなじみのWBS(Work Breakdown Structure)。ただ、名前からして「なんだか機械的で、まるでExcelとらめっこしそうなやつ…」という印象を持ちがち。でも大丈夫。 今回は、WBSを「笑いとスイーツ」で優しく分解してみましょう!
WBSってなに?
ざっくりと言うと、
「プロジェクトでやることを、漏れ漏れなく、全部分けてツリー一覧表」
です。WBSは「お菓子作りレシピの分解図」みたいなもの!
ケーキ作りプロジェクトで例えるWBS
あなたが「誕生日ケーキを作るプロジェクトのPM」とします。
このとき、WBSはこう書かれます:
0.プロジェクト目標
「誕生日ケーキを完成させる」
1.材料の準備
卵を買う
小麦粉を計る
生クリームを冷やしやすい
2. ケーキ本体の作成
スポンジを焼く
スポンジを冷ます
デコレーションする
3. ケーキの納品
写真を撮る
ケーキを箱詰めする
誕生日パーティー会場へ移動
WBSとは「仕事を分けて、箱にしまう技術」
WBSでは、プロジェクトを「作業のかたまり(ワークパッケージ)」に分けていきます。
- 「材料買う」っていう箱
- 「焼く」っていう箱
- 「届ける」っていう箱
この箱たちを上から順に、徐々に細かく分けていくことで、「やるべきことを全部洗い出す」わけです。
なぜWBSが重要なのか
- 抜け漏れを防ぐ
→ 絶対やってはいけないことが全部見える! - 見積りしやすい
→各パッケージを見える化 - 誰が何するか割り振れる
→ ワークパッケージ単位で担当をアサイン! - 「仕様にないことやるな!」の線引きになる
→ スコープ管理のカギ!
PMP試験でのポイント
| 覚えておくべきこと | 内容 |
|---|---|
| WBSはスコープ・ベースラインの一部 | 「スコープ記述書+WBS+WBS辞書」 |
| ワークパッケージ | WBSの一番下具体的な作業単位(タスクではない) |
| 構造はトーナメントのような階層構造 | どんどん分割していく(階層構造) |
| 100%ルール | 親要素は子要素すべての合計(抜け漏れ×) |
| 「要素に“名詞”を使う」 | 作業ではなく、成果物として本来のが一般的 (例:「スポンジ作成」ではなく「スポンジ」) |
| 覚えておくべきこと | 内容 |
|---|---|
| WBSはスコープ・ベースラインの一部 | 「スコープ記述書+WBS+WBS辞書」 |
| ワークパッケージ | WBSの一番下具体的な作業単位(タスクではない) |
| 構造はトーナメントのような階層構造 | どんどん分割していく(階層構造) |
| 100%ルール | 親要素は子要素すべての合計(抜け漏れ×) |
| 「要素に“名詞”を使う」 | 作業ではなく、成果物として本来のが一般的 (例:「スポンジ作成」ではなく「スポンジ」) |
よくあるWBSあるある
- 「WBS作ったら仕事が終わった気になる」
→実はここからが始まる! - 「めっちゃ分解したけど、実行フェーズで「何だったらいいの?」って言われる」
→ WBSが「成果物ベース」じゃないと、作業のイメージが湧かない… - 「その作業、WBSにならないからスルーしました」
→ うっかり「スコープ外」扱いされる悲劇…
WBSまとめ
| WBSとは… | 意味 |
|---|---|
| 全体を分解 | 目標 → 成果物 → 作業単位段階的に検討 |
| 箱詰め思考 | 各要素を「抜けなく」分類して管理 |
| スコープ制御 | 「これやしからん!」と明確に宣言できる |
| PMPの重要用語 | 計画プロセス群の要(中心)です! |
| WBSとは… | 意味 |
|---|---|
| 全体を分解 | 目標 → 成果物 → 作業単位段階的に検討 |
| 箱詰め思考 | 各要素を「抜けなく」分類して管理 |
| スコープ制御 | 「これやしからん!」と明確に宣言できる |
| PMPの重要用語 | 計画プロセス群の要(中心)です! |
スコープクリープ
PMの天敵とも言えるこの言葉──スコープ・クリープ(Scope Creep)。名前はちょっとカッコイイけど、プロジェクトマネージャーにとっては横から忍び寄るホラー映画の怪物みたいな存在です。では今回もたっぷりに、優しく解説していきます🍰
スコープ・クリープとは?
一言で言えば、
「気がついたら、やることが増えてる」現象。 じつは、正式な変更手続きナシだったのが原因!?
こんな感じです
👨💼「あのぅ…ついでにこれもお願いしていい?」
👩💻「えっ…前に言ってなかったんですよね?」
👨💼「まあ、大変じゃないですよね?頼むよ〜♪」
👩💻(あ、出た。スコープクリープ…)
ケーキ屋で例えるスコープ・クリープ
あなたがPMとして「結婚式のケーキを作る」プロジェクトを管理しています。
最初のスコープ(やること)は:
- 3段のチョコレートケーキ
- 生クリームデコレーション
- 新郎新婦の名前入りプレート
もしかして、もしかして…
👰「やっぱ中にイチゴも入れて」
🤵「花火も仕込んでくれる?」
👰「ドライアイスでもモクモクってのも…!」
あなた(PM)「えっっっっ……(聞いてない)」
スコープが徐々に増えてきています…それがスコープ・クリープです。
なぜ「クリープ」なの?
「クリープ(creep)」は英語で「忍び寄る」とか「少しずつ進む」って意味です。
そうですね、スコープクリープは…
💀「こっそり」「ジワジワ」「気づいたら取り返しがつかない」
という、怖い特徴を持っているわけです。
なぜスコープクリープは問題なのか?
| スコープクリープの問題 | 内容 |
|---|---|
| スケジュール遅延 | 追加作業のせいで納期ぎりぎりに |
| 予算オーバー | 見積もってない作業のせいで負けに |
| チーム疲労問題 | 「え、これもやるの?」の連続でモチベダウン |
| 顧客トラブル | 「聞いてない!」または「やったのに認めてもらえない!」 |
| スコープクリープの問題 | 内容 |
|---|---|
| スケジュール遅延 | 追加作業のせいで納期ぎりぎりに |
| 予算オーバー | 見積もってない作業のせいで負けに |
| チーム疲労問題 | 「え、これもやるの?」の連続でモチベダウン |
| 顧客トラブル | 「聞いてない!」または「やったのに認めてもらえない!」 |
スコープ・クリープを防ぐ方法
- スコープ・ベースを明確にする
→ 「やることリスト」は文書でしっかり残しておきます! - 変更管理プロセスを使う
→ 追加や変更は正式な申請&承認フローをよろしく! - 「イエスマンPM」にならない
→ 「それ、スコープ外ですので」と勇気を! - ステークホルダーと密なコミュニケーション
→ 勝手に期待値がふくらまないように、丁寧に説明!
PMP試験での用語整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| スコープクリープ | 正式な変更プロセスなしでスコープが拡大すること |
| Integrated Change Control(統合変更管理) | スコープ変更を正式に処理するプロセス |
| スコープ・ベースライン | スコープを明確化&固定する基準。クリープの防波堤! |
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| スコープクリープ | 正式な変更プロセスなしでスコープが拡大すること |
| Integrated Change Control(統合変更管理) | スコープ変更を正式に処理するプロセス |
| スコープ・ベースライン | スコープを明確化&固定する基準。クリープの防波堤! |
現場あるある
- 「ちょっとだけ」って言われたけど、1週間かかった
- 誰も知らない作業が終わった
- PMが「頼まれたら断れない性格」で大炎上
- 「最初より完成品が豪華すぎる」のに、誰も褒めてくれない
まとめ:「スコープクリープ=プロジェクトの『勝手にミッション増やす屋』」
- 変更は「正式な手続き」を通すべし!
- スコープ・ベースラインを「防波堤」に!
- PMはスコープガードマン!
- 「ついでにやっといて」は禁句!
スコープクリープを許すと、プロジェクトは「便利屋」へと変わり、
最後には「誰も得しないカオス状態」になるので注意!
PMP用語解説リンク集
プロジェクトの開始と計画
プロジェクト手法の理解と選択
スコープのマネジメント
スケジュールのマネジメント
予算のマネジメント
品質のマネジメント
資源のマネジメント
コミュニケーションのマネジメント
リスクのマネジメント
調達のマネジメント
ステークホルダーエンゲージメント
終結、ガバナンス、統合
作業の実行とマネジメント
プロジェクト作業と管理
変更管理、課題管理
パフォーマンスの高いチームを作り支援する
チームの育成
エンパワーメントと指導
共通理解の形成
チームのパフォーマンスを支援する
障害を取り除く
変化への対応とPDCA
Udemy PMP模擬試験講座
Udemyとは、2010年にアメリカで創業された教育系スタートアップ企業で、2015年にベネッセと連携して日本に展開しています。Udemyは、さまざまな講師の講義を選択でき、受講料も大変安いのが特徴です。日本ではIT業界や若年層を中心に普及が進んでいて、PMP試験対策のラインナップも豊富です。
これだっ!!Udemyで日本人に真にオススメできる模擬試験講座を作るぞ!ということで半年以上かけて作りました。
↓実際の画面
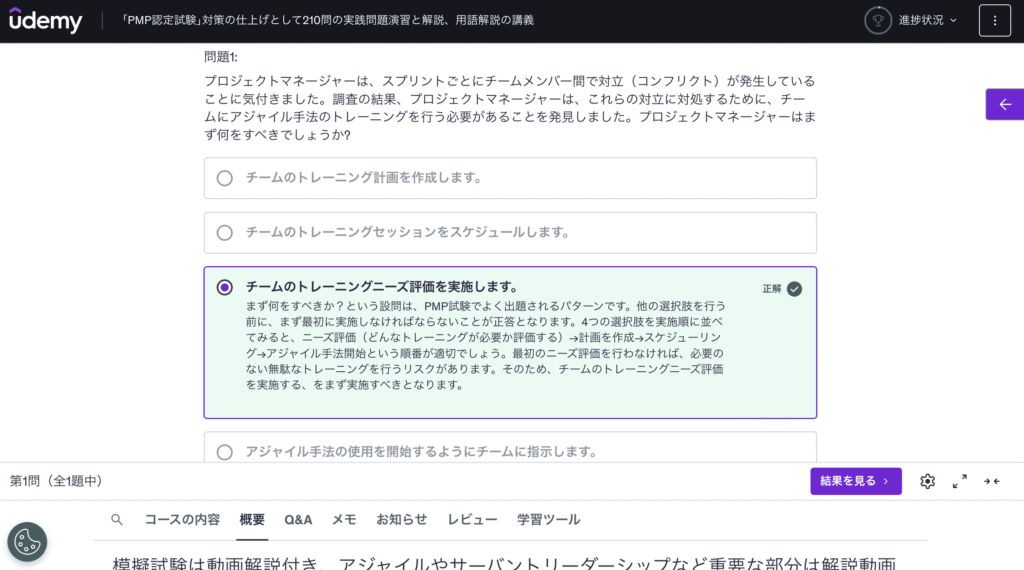
本講座は、基礎の復習と、仕上げの模擬試験練習ができる講座となっています。
・アジャイルなどの重要用語解説動画
・10問ごとの小テスト(スキマ時間活用)
・210問の模擬試験と解説
・模擬試験の解説動画
大変好評いただいており、数あるUdemy講座の中から3%程度が選出される、Udemy Business講座の仲間入りを果たしました。皆さまの日頃のご愛顧に感謝いたします。
UdemyPMP 模擬試験講座が1500円。ベストセラー講師が作成
模擬試験・ミニテスト・解説動画付き